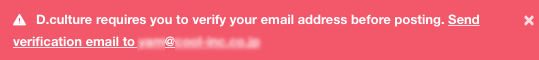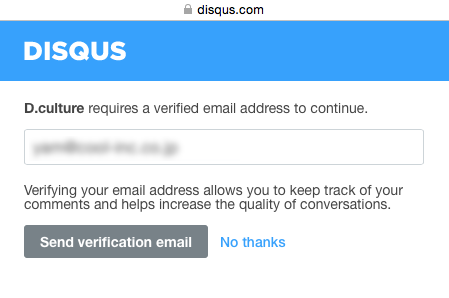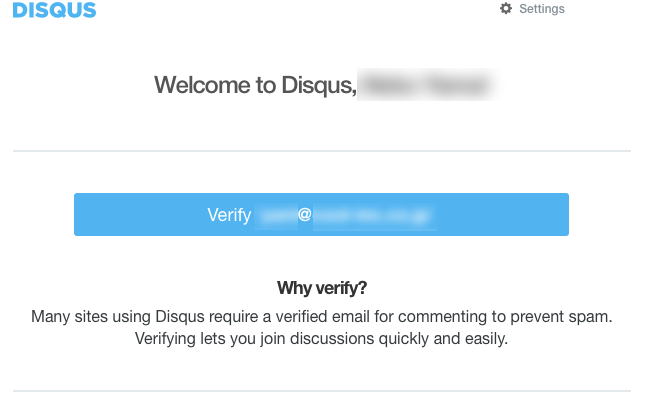花岡伸和氏
[一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 副理事長]
アテネへの切符を手にする
福祉公社で公務員として働きながら競技に打ち込み、私は徐々に力をつけていった。国内レースで上位に食い込めるようになったのは20歳代前半の頃。そうなると、当然、次は「世界」が射程に入ってくるようになる。しかし、海外に目を向けると、プロフェッショナル・アスリートとしてフルタイムで競技に打ち込んでいる強豪たちがゴロゴロいるのが現実。そうした選手たちと伍して戦っていくには、自分にはまだ決定的に力が不足していることを痛感せざるを得ない。口先で「パラリンピックに行く」と放言しているだけでは、とても目標を実現できない──そのことに私はようやく気付くようになった。
まず、環境を変えようと思った。その頃、日本の障害者スポーツの世界でも、フルタイムで練習に明け暮れる選手がポロポロと現れはじめていた。私もフルタイムか、あるいはそれに近い形で練習に打ち込める環境に身を置こうと思った。そのとき、縁あってお世話になることになったのが、本田技研の子会社であるホンダ太陽という企業。大分に拠点を置く、障害者のスポーツチームを擁する企業で、当時の実業界では障害者スポーツを支援する唯一無二の存在だった。
私は5年間務めた福祉公社を辞して、大分に渡った。公務員としての安定した生活基盤を捨てることになったが、なにかを得るにはなにかを捨てる覚悟を持たなければならない。私は、どうしても「世界」に近づきたかった。そのためには安定した生活基盤という財産をなげうとう──私に躊躇はなかった。
ホンダ太陽では、文字通り競技中心の生活を送った。仕事は定時よりも早い時間に上がり、長時間を練習に費やす。練習内容も変わった。余暇を練習時間に当てていた頃とは違い、より計画的なプログラムに沿ってトレーニングすることが可能になったのだ。その成果は、さっそく現れた。さまざまなレースで常に日本のトップクラスに名を連ねることができるようになったのである。アテネへの道が見えてきた。夢でしかなかったパラリンピック出場が、ようやく現実的な目標となった。
さまざまな国際大会にも出場した。世界レベルの走りを体感する中で、その最高峰たるパラリンピックへの思いが募った。私は、ますます深く練習に没頭するようになった。そして、アテネパラリンピックの前年である2003年、私の努力、私の賭けのすべてが報われるときがようやくやってきた。その年、私は1500メートルとフルマラソンで日本記録を樹立、国際マラソンでの優勝も経験したことで、アテネへの切符を手にしたのである。
すべてが自己責任の世界
そして再び、選択のときがやってきた。アテネで自分の実力を十二分に発揮し、納得のいく成績を収めるためには、今の環境ではまだ生ぬるいと考えるようになったのだ。1日24時間を練習に費やせる環境に身を置きたいと思った。そう、私は日本ではまだ数少ないフルタイムのプロフェッショナル・アスリートとしてやっていきたくなったのである。その思いの背景には、やはりアメリカ体験があったように思う。自分の努力と才覚だけで、障害者でありながらプロフェッショナル・アスリートとして自立しているアメリカの競技者たち──彼らの姿は、私にとって一つの理想だった。
だが、日本では障害者がプロアスリートとして生きていく上での土壌というものが、まったく形成されていないのが現実。選択の重さは、福祉公社を辞めて転職したときの比ではない。熟考した。一つの計画を立てた。公務員時代の5年間で、私はある程度まとまった額の貯蓄を残していた。それを取り崩していけば、1年間ぐらいは働かずとも食べていける。ならば、とりあえずアテネパラリンピックまでの1年間限定でプロとしてやってみよう──それが私の結論だった。
プロになるからには、退路を断つ覚悟が必要だった。私は甘えを捨てるため、まったくの新天地で生活を組み立てなおそうと考えた。地元の大阪に帰るという選択肢もあったのだが、私はあえて東京への移住を選んだ。まさに、背水の陣だった。
しかし、物事はそううまくは運ばない。東京に居を移してすぐに、私は自分の見通しの甘さを痛感させられることとなった。あまりにも激しい環境の変化、それが私を萎えさせてしまったのだ。最初の2カ月ほどは、ほぼ自宅に引きこもりきりという体たらく。もし、スポーツという拠り所がなければ、わたしはあのままダメになっていたかもしれない。
それでもなんとか体勢を立て直し、本格的な練習を再開した。すると今度は、自由ゆえの不自由という難問が立ちはだかった。それまでは仕事の時間ありきの練習時間だったのが、今は1日24時間を自由に使える。24時間の使い方を、ぜんぶ自分で組み立てていかなければならない。それは、大変な作業だった。ありあまる自由は、かえって人を途方に暮れさせるのだということを、私ははじめて知った。
セルフコントロールの重要性を、私は痛感した。たとえば、練習ひとつをとってみてもそうだ。フルタイムを練習に使える──そう考えると、どうしてもオーバーワークになりがちだった。そのため、この時期、私はよく故障した。故障してブランクができると、それを取り戻すためにさらにオーバーワークに走り、また故障するという悪循環。当然のようにレースに出ても成績は振るわず、焦燥は募るばかりだった。
この時期をなんとか乗り越えることができたのは、とにかく後には引けないという気持ちがあったからだと思う。それと、幸いなことに周囲に私を支えてくれる大切な人たちがいたことも大きかった。調整はぎりぎりで間に合った。アテネパラリンピックの開催は2004年の9月。その前月に行われたレースで、私は自己記録を大きく更新する走りができたのである。まさに、薄氷を踏むような1年間だった。
そのように大変な思いをしたプロフェッショナル・アスリート生活だったが、今振り返ると、私はトライしてみて本当に良かったと思う。なぜか。人間、なにが起こっても最後は「自己責任」であるということが、身に染みて理解できたからである。そう、フルタイムを自由に使える環境に身を置くことは、すべてのことに自分で責任を持たなければならないという厳しさを突きつけられる体験だ。なにが起こっても最後は「自己責任」。これは、プロフェッショナル・アスリートに限った話ではないと思う。
それまでの私には、人生の大切な部分を人任せにしてきたところがあったように思う。人に期待し、自分で担うべき選択や役割や義務を人任せにし、それでうまくいかないとやめてしまう──そんな甘えが、確かに私にはあった。それが、プロフェッショナル・アスリートとして生きた1年間で、すべては「自己責任」であるということを学んだことにより、だいぶ改善された気がしている。その意味で、やはりあの1年間は、私が成長していく上での重要な糧となったと今では考えている。

アテネパラリンピック(2004年)の車いすマラソンで6位、ロンドン(12年)で5位に入賞した車いす陸上の国内トップアスリートが花岡伸和氏。マラソンを引退後は後進の指導に力を入れる一方、手でペダルをこぐ自転車「ハンドサイクル」に転向し、同競技での東京パラリンピック(20年)出場を目指している。