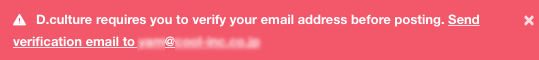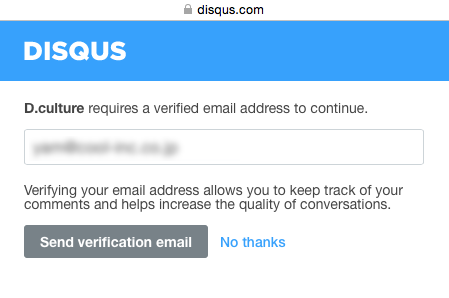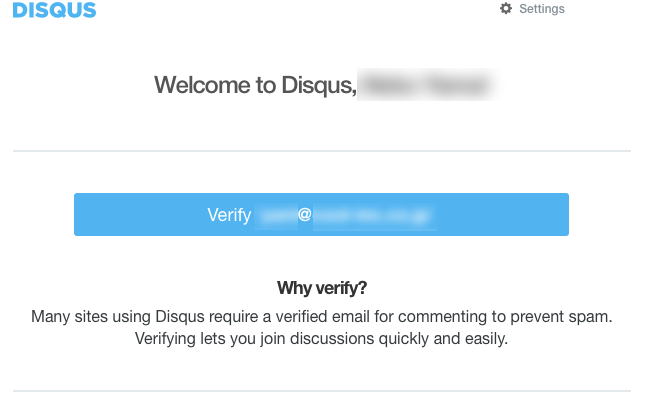首藤智子さん(仮名)
[会社員]

元・動物病院の看護師で、いまは人材派遣会社でOLとして働く首藤智子さん(仮名・38歳)は、重度の鬱病で就労不能だった時期を長く持つ。現在の会社では入社4年目だが、「サポート社員(非正規)」としてのステージも上がり、正社員への道も見え始めたところだ。「時給も上がって、ようやく生活保護を抜けるメドも立ちました」と明るく笑う彼女の壮絶な過去と、前向きに生きる現在を紹介する。
人は一人では生きてはいけない
待ち合わせの駅にカジュアルなスタイルで現れた首藤さん。グリーンのジャケットの粋な着こなし方を見ても、なかなかの「おしゃれさん」だということが分かる。
「会社にもネイルしていきますし、一時期はエクステも着けていました」と悪戯っぽく笑うその表情は実年齢よりかなり若く見え、とても「生きるか死ぬか」の壮絶な過去を経てきた人とは思えない。近隣の喫茶店に入り、まずはもっとも訊きにくいこと──障害を抱えるに至った経緯について尋ねてみた。
元々、動物が大好きで、動物関係の仕事に就くことが小さな頃からの夢だった。念願かなって動物病院で看護師としての職を得たのは27歳のとき。そこから彼女の苦難の道のりが始まった。「結局、動物が好き過ぎたんでしょうね」と首藤さんは言う。
「病院にやってくる一人ひとりの子たちに情が移ってしまって、『みんながわが子』みたいな感覚に陥ってしまったんです。でも、病院ってやっぱり生き死にの場所じゃないですか。自分の子が為す術もなく死んでいく様子を日常的に看取る職業って、ハタからは想像がつかないほど私にとってはハードだったんです」
「結局、仕事を選び間違えたということでしょうか」と時折、涙ぐみながら話す首藤さん。そんなある日、決定的な出来事が起こった。病院で20年飼育してきた猫が腎臓を患い、安楽死させるより他に手立てがない状態に陥ってしまった。
その猫は首藤さんにとって、文字通りわが子以上の存在だった。しかし、現実は過酷だ。その猫に安楽死の処置を施す役割が、病院で管理している動物たちのメインの看護師であった彼女の手に委ねられることになってしまったのだ。医師もその他のスタッフも、おそらくは首藤さんにとってその猫が持つ“重み”をまったく理解していなかったのだろう。
「いまとなっては他に選択肢がなかったことはわかるんです。もう20歳だし、延命措置は無意味でした。でも、当時の私はわが子を自分の手で殺したという罪悪感と後悔の念でいっぱいで……そこからですね、気持ちが一気に落ち込んでいったのは」
わけもなく涙が流れるような情動失調が生じ、気が付けば真っ暗な部屋で一人うずくまるような状態に陥っていた。鬱病の発症だった。友人に伴われ精神科病院を訪れると、医師から「即、入院」と告げられた。しかし、彼女は入院を選ばず、一時退却のつもりで地方の実家に戻った。この選択が裏目に出た。
家族はメンタルの病についての理解を持たず、地方特有の迷信的な解釈で彼女の状態を捉えてしまった。もっとも近しい者たちの中で孤立して過ごした1年半。この時期が「どん底でした」と首藤さんは言う。結局、逃げるように東京に舞い戻り、再び動物病院に復帰した。しかし、長くは続かず、バイク通勤の途中でICUに運び込まれるような大事故を起こしたことをきっかけに彼女は職を辞した。そして、生活保護で露命を繋ぐこととなった。
闘病の日々が続いた。ただ無為な時間だけが急速に流れていった。この時期のことを、彼女は「あまり思い出したくない」と言う。病状が落ち着くまで数年間がかかった。主治医から就労にOKが出た。彼女は躊躇うことなく働くことに決めた。
「やっぱり人間、一人では生きていけないと思うんです。この社会では、みんな働くことを通して支え合って生きている。ですから、その支え合いの輪の中に働くことを通して参加するのは当たり前のことだと思っています。自分だけ一人で生きていこうと思ったら、無人島にでも行って自給自足するしかありませんからね」
障害者枠の開拓者として
就職はすぐに決まった。障害者専門の就職エージェントを通していまの会社に採用されたのは就職活動をはじめて3カ月後のこと。本部スタッフ約50名、派遣スタッフ4000~5000人を抱える中堅どころの人材派遣会社である。ここで働き始めた頃のことを「とにかく楽しかった」と首藤さんは回顧する。
「パソコンに向かって仕事をする、いわゆるOL職というのは初めての経験でしたので、すべてが新鮮でした。はじめは入力作業やオフィスの清掃など簡単な仕事から入って、徐々に集計作業やエクセルを使った資料集めなども任されるようになりました。そんな風に責任ある仕事に携わらせてもらえるようになったことも嬉しかったですね」
仕事が楽しいと、病状もまた変わってくる。「自分が楽しめているときは、たぶんすべてが上手くいくんです」と首藤さんは言う。だが、それが上手くいかなくなった時期もあったそうだ。
その会社で、首藤さんは障害者枠での採用のフロントランナー的存在だった。当初、同社で働く障害者は知的が3名、精神が1名の計4名。有能な首藤さんは入社1年目にして障害者枠のリーダーに抜擢された。そして、次々と入社してくる後輩の障害者たちの面倒を看る役割を委ねられるようになった。
「そこでいろいろな不満を持つようになったんです。障害者枠というのははっきり言って仕事上のハードルは低く設定されていますから、ある程度、手を抜いて仕事をしても許されてしまう。ところが彼ら・彼女らをまとめる役割の私はそうはいきません。上司からの要求も厳しいし、こんなに仕事を頑張っている自分とサボってばかりいる子たちが同じ時給で働いているということに矛盾を感じ、『なんだよ』という気分になってしまったんですね」
サボってもゆるされる存在と一生懸命働くことを余儀なくされる彼女が同じ時給で働く──たしかに「なんだよ」と言いたくなるところだ。彼女は、この状況をどう打開したのだろうか。
ひとつのきっかけがあった。首藤さんが入社2年目のとき、やはりメンタルを病む27歳の女性が入社してきた。彼女もまた極めて有能な女性だった。しかも、年齢的にも首藤さんより『伸びしろ』のある若さだ。社内で障害者枠のリーダーを首藤さんからその女性にシフトさせる動きが生じた。
上司は首藤さんに「キミの負担をかんがみて、責任を分散させようと思ったんだ」と説明したというが、彼女にとってみれば事実上の降格と受け取らざるを得ない人事である。大いに不満を抱いた。そこで、上司とその女性と首藤さんの3人で話し合いの場をもった。
「その子とは気が合って一緒に飲みにいったり遊びに行ったりする仲になっていたんですが、その話し合いの席で彼女が言ったんです。『そんなの首藤さんが可愛そうじゃないですか』。私、思わず笑ってしまったんですけど。『ああ、私って可愛そうなんだ』って。そこから何かが吹っ切れたんです。だったらすごい量の仕事をこなして、この会社には私がいなければダメなんだという環境を作って、その上で辞めてやるって」
それまで、首藤さんは社内で典型的なイエスマンだった。上司の言うことに対し、なんでも「はい、はい」と応え、口ごたえするようなことは一切なかった。しかし、その出来事があってからそうした“従順な私”を演じることを止めることにした。言いたいことははっきり言う。理不尽な要求にははっきりNoという。
結果、どうなったか。彼女の意見は、それが正当なものであるかぎり、きっちりと通るようになった。仕事も以前よりもずっとやりやすくなった。もちろん、彼女が仕事で結果を出し続けていることが前提なのであるが、首藤さんは社内でのサバイバル術を見つけたといえるだろう。
この4月には時給交渉をし、しっかりと昇給を勝ち取った。生活保護から完全に脱却する道筋が見えた。そして今、彼女は上司から「わが社の障害者雇用の開拓者になってくれ」と言われているという。
そんな彼女に、最後に障害を抱えながら働くコツは何かと問いかけてみた。
「セルフコントロールに気を付けることでしょうか。1日1回は必ず笑うようにするとか。同じ1日24時間なら、愚痴を言ったり文句を言ったりするより、楽しく過ごした方がずっといい。だから、人の言葉や態度に惑わされずに、自分を信じることにしています。そうすれば、なにかメゲるようなことがあっても人のせいにしたり、あるいは病気のせいにしたりすることもなくなる。なにがあっても冷静でいられると思うのです」
「首藤さんは強いですね」、そう筆者が言うと
「みんなにそう言われます」、花のように笑った。