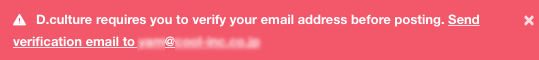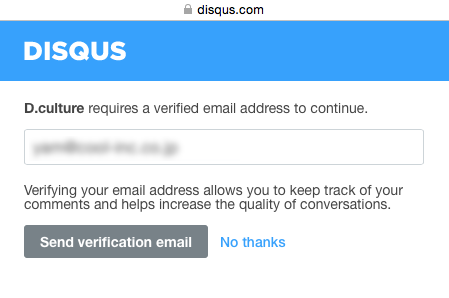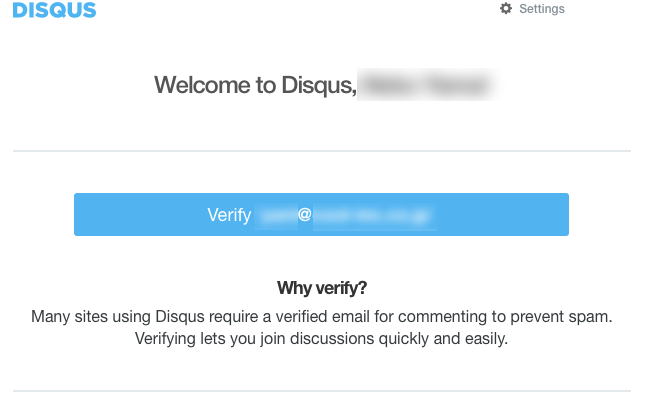花岡伸和氏
[一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 副理事長]
必要なのは「競技力」だけではない
今回は少し難しい話になるかもしれないが、アスリートという存在がなぜ社会で必要とされるのか──アスリートの存在意義について考えてみたいと思う。
私は、こう思う。アスリートの存在意義とはやはり、社会の中での一つのモデルを提示することだ、と。そのモデルの提示とは、子供たちや同じ競技を志す人たちにとっての一つの「あこがれのカタチ」を示すこととほぼ同意義だが、そこには狭い意味と広い意味がある。狭い意味での「あこがれのカタチ」とは、簡単にいうと競技自体の魅力やそのアスリートが競技をしている姿の格好良さなどとイコールである。一方、広い意味での「あこがれのカタチ」とは、そのアスリートの「生き方」と大きく関係してくる。そのアスリートが一競技者として、また一社会人としてどのように生きてきたか、人々のあこがれとなれるような生き方をしてきたか──そんな「生き方」のモデルを社会に示すことこそ、本質的な意味でのアスリートの存在意義であると私は思う。
話は少し迂回するが、今の日本のパラリンピックスポーツ界には、一つの致命的欠陥がある。それは、あるアスリートにあこがれを抱き、その競技を志したとしても、受け皿がほとんど整備されていないという状況だ。たとえば健常者のスポーツに関して言えば、陸上競技だけでもクラブチームが各地域にあるし、その他のスポーツにしても少年野球・少年サッカーとさまざまに受け皿が用意されている。しかし、パラスポにはほとんどそれがない。どんなスポーツでもそうだが、競技の底辺を広げ、競技全体のレベルを上げていくには、あこがれの受け皿、つまり競技への「入り口」の部分が整備されていることが前提だ。それがなされていないがゆえに──2020年を目前に控え、パラという言葉がこれだけ浸透してきても──日本ではパラスポの認知が一向に進まないのだ。それは、非常に残念な状況である。
では、なぜ日本ではパラスポの入り口が未整備なのか。いろいろな要因があるが、決定的なのは指導者不足だと私は考えている。スポーツ(だけではなく何事もそうだと思うが)では基礎練習がなによりも大事であるが、その基礎の部分を教えられる指導者が不足していることが、入り口の整備が進まない最大の要因ではないか。
その指導者に関していうと、やはり元選手が最も有力な候補であるが、ここで残念ながら生きてしまうのが「名選手必ずしも名指導者にあらず」という格言。いくら競技力が高くても、それだけでは名指導者にはなれない。トップアスリートにあこがれた子供たちが競技力を向上させるだけでなく、人間としても分厚く成長していくためには、彼らを指導するアスリートの側が、やはり人としての「生き方」のモデルを示す必要がある。言葉を換えれば、そのアスリートがどんな「生き方」をしてきたかが試されるのだ。そうしたアスリートとしての存在意義をすっ飛ばして、メダルの数ばかり議論してもまったく無意味であると私は思う。
生死をも自己管理する強靱な生き方
さて、その「生き方」のモデルという意味で、最近、私はあるパラリンピアンの事例に非常な感銘を受けた。マリーケ・フェルフールトというベルギーの車椅子陸上選手のケースである。
彼女は、リオ・パラリンピックがはじまる前にフランスの新聞のインタビューを受け、こう応えた。「私は、リオの大会が終わったら安楽死する」、と。ちなみにベルギーでは本人と医師の同意があれば安楽死は合法なのであるが、この発言は大きな話題となった。マリーケ選手は進行性の病に冒されており、スポーツの練習をしている時期とパラリンピックに向けて大事な時期以外の時間をほぼ、治療に費やしているという。その治療が大変な苦痛を伴うものであるということで、一般の間では「彼女はそういう苦しみに耐えきれずに死を選ぶのだ」という見方が大勢を占めていたようだ。

マリーケ・フェルフールト選手と
だが、私は「違う」と思った。それは自らの生死をも自らの意思でコントロールしようとする、ある意味、究極の自己管理ではないかと思ったのだ。障害者であろうと健常者であろうと、人間に与えられた時間というのは有限である。その有限な時間を完全にコントロールし切り、さらにその先にある死までも自己管理しようとする──見事な「生き方」のモデルだと、私は思うのだ。
彼女はリオで銀メダルを取った後の記者会見で、記者の質問に対し、こう応えている。
「ベルギーに帰ってすぐに死ぬわけではないから安心してください。私はこれからスカイダイビングをやりたいと思っているし、2020年の東京も見に行きたい。やりたいことはまだまだあるから」
そして実際、ベルギーに帰国後、すぐにスカイダイビングの練習をはじめているという。「東京も見に行きたい」と言っている時点で競技者としては引退の意思を固めていることは明白であるが、そうして一つのチャレンジを終えて、すぐにまた次のチャレンジをはじめているのだ。有限な時間の中でのチャレンジングな「生き方」──その究極のモデルが彼女の事例であると思う。しかも、「死」という極めて重たいテーマに対し、「やりたいことはあるけど、やりきったら死ぬよ」と非常にポップなスタイルで回答を出した──私はそこに確固たる美学をみる。
マリーケ選手の事例は少々、極端なケースかもしれないが、彼女のように広い意味での「生き方」のモデルを示すことこそ、アスリートの本質的な存在意義なのではないか。私はそのように考えるのであるが、どうだろう?

アテネパラリンピック(2004年)の車いすマラソンで6位、ロンドン(12年)で5位に入賞した車いす陸上の国内トップアスリートが花岡伸和氏。マラソンを引退後は後進の指導に力を入れる一方、手でペダルをこぐ自転車「ハンドサイクル」に転向し、同競技での東京パラリンピック(20年)出場を目指している。