実方裕二氏
[caféゆうじ屋店主]

料理人としての原点は母から教わった手料理のレシピ
重度障害者の人生行路には事実上、養護学校を出ると施設に入る以外にほとんど選択肢がない。だが、実方さんはそれでも、どうしても自立生活が営みたかった。そこには、「重度障害者、こうあるべし」というようなある種の規範への反発心があったという。
「僕には兄と姉がいるのですが、僕が高校の頃、僕の介助はほとんど兄がやってくれていた。その頃、兄は大学生だったのですが、僕を寝かしつけると、夜、遊びに出かけるわけです。『なんで僕だけ早く寝なくちゃいけないんだよ』──そんな風に思っていましたね」
実方さんは19歳にして家出同然のカタチで一人でアパート暮らしを始めた。そして、先輩の見様見真似で障害者運動にかかわりを持つようになる。その頃の事を、実方さんは「ただ運動の中で掲げているスローガンを追いかけているだけという感じでした」と回顧する。
「生活と運動が分かれている状態でした。たとえば地域の人たちと一緒に生きるといっておいて、僕の毎日といえば夕方から会議に出て、それが終わるとただ呑みに行って、夜中に弁当を買って帰り、食べて寝る。そして昼過ぎまで寝ていてパチンコ屋で遊び、そのまま会議に出るという繰り返しだったのです」
そんなある種、自堕落な生活に転機が訪れたのは、一人暮らしをはじめて10年ほど経った頃。音楽好きの実方さんのバンド仲間に「裕二、障害者だからといって甘ったれてるのも大概にしろ」と叱咤激励されたことがきっかけだった。
その頃から実方さんは、おぼろげながら食べ物で仕事がしたいと考えるようになった。一人暮らしをはじめて、自分の手でつくれなくても介助者に伝えながら作るのが重度障害者の調理法だという感覚は身につきだしていた。出来上がったものは評判もよく、食堂のようなものをやりたいという思いが芽生えるようになった。
「料理人としての僕の原点は、母親の手料理。母親は料理好きで、僕が小さい頃、食事介助をしてくれていたのですが、そのとき、僕に料理を食べさせながらその作り方をいろいろ教えてくれたのです。その体験がなかったら、料理人としての僕はあり得ませんでした」
障害者の自立生活のモデルをつくりたい
だが、それから実際に食べ物で商売できるようになるまでには、さらに10年がかかった。その間、実方さんは運動から離れ、自分の“中身づくり”に終始したという。
重度障害者が料理をつくるという感覚のない世の中では、食堂をやりたいなどという勇気はなかなか出ない。でも、介助者に手伝ってもらいさえすれば自分の料理はできる。複雑な思いが交錯する中、彼の背中を押したのは、やはりバンド仲間だった。折からの激辛カレーブームの中、オリジナルレシピのカレーづくりにハマっていた彼に、先の叱咤激励をくれた友人から「自分たちでライブハウスのような企画をやるから裕二が責任をもって飲み物や食べ物を用意しろ」という思いやり深き提案がなされたのだ。それをきっかけに、実方さんは約10年にわたりカレー販売を手掛けながら、電動車椅子に乗ってオリジナルレシピのカレーやケーキの宅配をはじめた。そして2012年caféゆうじ屋のオープンにこぎつけたのである。
「ゆうじ屋を始めるにあたっては、目標が二つありました。一つは先に述べたように僕は堕落した生活を送っていた時期もありますから、自分の生活をまともなものにすること。もう一つは、障害者の自立生活というのはパターンが決まっていて、親の家から出て介助者の手を借りながらアパート暮らしをし、そして運動をやる。でも、僕は、それだけじゃなくてもいいんじゃないかと思うのです」
「障害者って、生き方を選べないんですよね」と、実方さんは続ける。
「養護学校を出ると、障害の軽い人は働くのですけど、重度障害者はほとんどが施設に行くしかない。そんな中、僕のように料理をつくっていろんな人に食べてもらいながら、それで生活を成り立たせることができれば、重度障害者の自立生活の一モデルになるのではないかと考えたのです」
オープン以来、ゆうじ屋はカレーやケーキのおいしい店として地元で評判だ。そうして店の営業を続ける一方で、実方さんは今でも「ゆうじ屋は 甘さを控えて 味を増す」と書いた看板を掲げ、昼過ぎから夜遅くまでケーキの移動販売に勤しむ。
「公園とかにも行くのですけど、最初は『変なおじさん、なにやってんの』と言っていた子供たちが、僕がお母さんたちと普通に会話しているのをみると、『このおじさん、ちゃんと話せるんだ』とわかるんでしょうねーー何回も通っていると子供たちだけのときでも『あ、ケーキのおじさんだ』と寄ってきてくれるようになる。それが、とてもうれしいですね」
生活お見合い
さて、どこまでもエネルギッシュな実方さんの活動は、食べ物商売だけにとどまらない。まず、パンクバンド「ラブ・エロ・ピース」のボーカリストとしての活動がある。同バンドはゆうじ屋でライブを開くほか、さまざまなイベントなどにも出演。実方さんは、自作の詞を独特の発声法でシャウトする。
また、かつて障害者運動にかかわり、それに失望した経験から、新しいカタチの障害者運動を模索し、展開しはじめてもいる。その一つが「生活お見合い」。これは一種の健常者と障害者の集いであり、互いのホンネをぶつけ合うことを趣旨としている。
「かつて運動をやっていたとき、それが自分の生活と乖離していることを感じていました。やはり、自分の生活とつながらないところで運動をしていても、それは単なるお題目になってしまう。ですから、健常者と障害者が互いの生活──『僕や私は、こうして生きてきました』ということをきれいごとじゃなく話し合うことで見えてくるものがあると思うのです。自分の醜いところもあえてさらけ出しあうことで相互理解を深めることにより、今のおかしな世の中に風穴を開けることもできるのではないか。そう思ってやっています」
こうして1日24時間では足りないほど八面六臂の活躍を見せる実方さん。最後に、「あなたをそうした活動に突き動かしているものはなんですか」と問うと、絞り出すようにして、こう応えてくれた。
「“伝えたい”ということが大きいです。僕には伝える責任があると思っています。ですから、正直な自分をさらけ出すのです」
実方さんが伝えたいこととは、おそらく重度障害者としてのご自身が見てきたものだろう。彼には強い使命感がある。その使命感が燃え尽きない限り、彼の挑戦が止むことはないはずである。


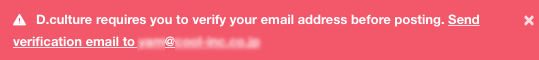
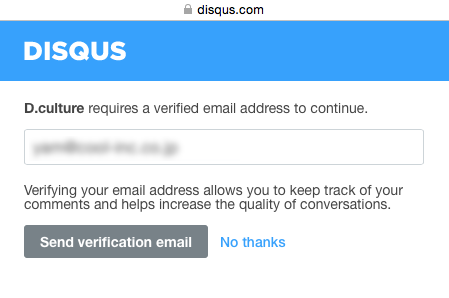
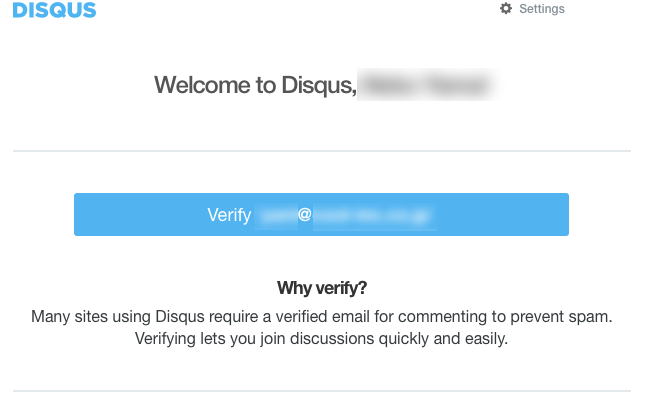
世間の空気が要請してくる「障害者らしさ」を突き破る感に共感。