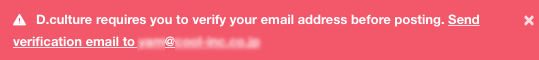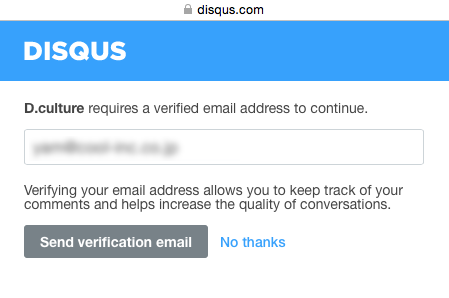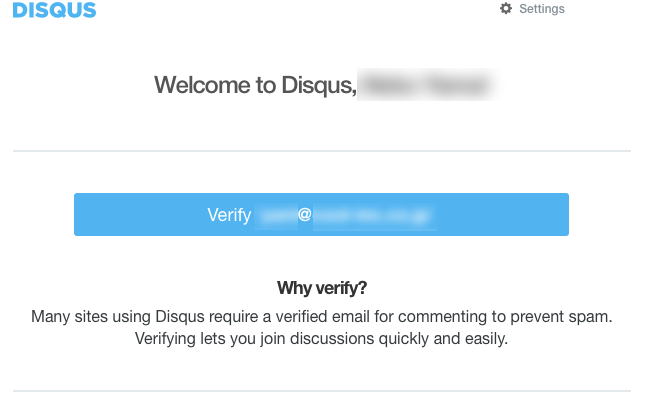花岡伸和氏
[一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 副理事長]
第5回 パラリンピックへの道(2)

半ば夢見心地での6位入賞
アテネ。マラソン発祥の地。すべてのマラソンランナーにとって憧れの地。私はそこに、ようやくたどり着いた。
マラトンからアテネまで──古(いにしえ)のギリシャ兵士たちがそこを走り、また、そこで息絶えたという伝説のコースを自分も走る。私の感慨は、言葉では言い尽くせないほどだった。現地に入った段階から、私は半ば夢見心地で、どこかふわふわしていた。パラリンピック初出場ということで心が浮き立っていたこともあっただろうし、アテネという地の神聖さに感染したようなところもあったように思う。
そんな状態でも、コンディションの方はベストの状態に持って行けていたらしい。後に私の様子を見ていた選手団の一人に聞いたところ、「アップのときに、花ちゃんはやると感じた」という。アスリートのタイプとして、私はいいときは120%の力を出すものの、コンスタントに100%を出せるというタイプではない。半ばバクチ打ちのようなタイプなわけだが、このときは120%で仕上げることができていたのだと思う。本番に強いことが、私の特徴の一つだ。それは、メンタルコントロールが比較的、上手いからだと思う。大舞台に立っても心を「いつも通り」の状態に保つところができる。レースでは、「一つやってやる」「絶対に勝ってやる」と意気込みすぎると、かえって良い結果を生まないものだ。私の場合、その辺の調整能力が高いのだろう。
さて、レースははじまる前から厳しいサバイバルゲームになることが予想されていた。高低差の激しいコースの特性と、夏のギリシャの酷暑がその理由だ。実際、パラリンピックに先だって行われたオリンピックのマラソンでは、絶対的な優勝候補といわれていたロシアの強豪が途中リタイアするという大番狂わせも起こっていた。
そして実際、レースは予想された通りの展開となった。上り坂のたびに集団が小さくなっていく、まさに「生き残り」レースとなったのだ。とにかく、コースの高低差がハンパなかった。上りももちろんきついが、下りも車いすだと60キロ以上のスピードが出るため非常に危険だ。私は一度、下り道を超ハイスピードで走っていたときに車輪をすべらせ、転倒しかけた。そのときには死を覚悟したほどだった。
とにかく先頭集団から離されないようにと、それだけを考えて走った。マラソンでは、集団の中でもいろいろ駆け引きがあるのだが、そのときは自分から仕掛ける余裕などまったくなかった。金メダルを取った選手がスパートをかけて「逃げた」ときも、まったく気づかなかった。気付いたとしても、追いかけるだけの気力・体力はとてもなかっただろうが……。
私は、自分が「走れて」いることを感じていたが、苦しい場面の連続の中でレースはもつれ、結局、五位集団の中を走りながらゴールのパナシナイコスタジアムに吸い込まれることになった。結果、メダルには手が届かなかったものの、総合六位。日本人では最高位でゴールすることができた。
やはり、海外勢は強いなと感じた。自分より速く走った選手がいたことへの悔しさもあった。しかし、私は結果には満足していた。自分にできるだけのことはちゃんとやれた、実力はちゃんと出せた──そんな達成感もあった。総じて、私のパラリンピックへの初挑戦は120%の出来だったといえるだろう。あの夏を忘れることは終生ない。
アスリートである以前に一人の人間であること
私たち陸上競技選手は、基本的にパラリンピック・スパンで人生を考える。結婚や出産といった人生の一大イベントはパラリンピックを終えたタイミングで──そんな感じである。私もご多分に漏れず、アテネを終えたところで結婚しようと考えていた。しかし、結婚を前提とすれば当然、人生設計を一から考え直す必要が出てくる。何の保証もないプロフェッショナル・アスリート生活を続けることは論外だった。なんとか安定した生活基盤を築かなければならない。
そこでレース後、アテネにチームメカニックとして同行していた車いすメーカー・オーエックスエンジニアリングの飯星氏に相談を持ちかけた。すると同氏から、今回のレース結果を考慮してウチで採用できるかもしれないとの返答をいただけた。私にとっては願ってもない話だった。ほかにこれといった選択肢も持たない身である。ほとんど迷うことなく入社を決めた。
ホンダ太陽などと比べるとずっと規模の小さな会社であるが、オーエックスエンジニアリングは堅実な企業だった。同社は私に、日常業務を怠りなく遂行することを前提として、レース用車いすの開発を含むレース活動の継続と、トレーニングのための勤務時間の優遇を認めてくれた。フルタイムで競技に専念していたパラリンピック前に比べ、練習時間に制限はできたものの、私は同社に勤めていた時代を非常に良い時代だったと思っている。なぜか。仕事を通しての「学び」が多かったからである。
中小企業ゆえに、同社では従業員一人ひとりがちゃんと仕事をしないと会社が回っていかない。一人ひとりが個人事業主──言ってみればそんな感覚だろうか。私は広報を担当していたのだが、年々、仕事の量も増え、仕事上の責任も増していった。カタログやパンフレットなどの紙媒体を制作したり、インターネットのホームページを作ったりといった経験は、その後の人生に非常に役立つものだった。そして、なにより仕事を通して社会で一つの役割を果たしているという手ごたえが、私にとっては得難いものだった。
私は、思う。アスリートにとって競技はもちろん大切だ。だが、私たちはアスリートである以前に一人の人間である。その立場で考えると、競技をファーストプライオリティとし、競技をほかのすべてに優先させるような生き方は、決して正しい生き方ではないのではないか。たとえば、仕事を通して社会で一定の役割を果たすこと。また、家族を作り、夫として、妻として、親としての役割を果たすこと。それもまた人生では不可欠な事であり、むしろ競技よりも優先させて考えるべき事項なのではないか。これは、古い家柄に育ち、子供のころから「男子たるもの自分の家庭を築き、それを守りつつ次代に引き継いでいかなければならない」と刷り込まれてきた私に特有の考え方かもしれない。しかし、競技にとらわれるあまり視野狭窄になってしまうのは、はっきりと間違いだと思う。
今、日本では2020年東京パラリンピックに向けて、企業が障害者スポーツに目を向けはじめている。私のところにも「いい選手がいたら採用し、育てたいのだが」といった相談が舞い込んでくる。私はそのたび、企業に「人間を育てるつもりでアスリート雇用してください」とお願いしている。ただ走るだけしか能のない人間──私はそんな人間を量産したくないのだ。企業が目を向けてくれるのはもちろん、ありがたいことなのだが、状況によってはいろんな弊害も出てくるのではないかと危惧するところである。
私たちはアスリートである以前に一人の人間なのだ──そのことを、とくに若い選手には忘れてほしくないものだ。

アテネパラリンピック(2004年)の車いすマラソンで6位、ロンドン(12年)で5位に入賞した車いす陸上の国内トップアスリートが花岡伸和氏。マラソンを引退後は後進の指導に力を入れる一方、手でペダルをこぐ自転車「ハンドサイクル」に転向し、同競技での東京パラリンピック(20年)出場を目指している。