増川ねてる氏
・東京ソテリア職員
・WRAPファシリテーター(アドバンスレベル)

常に回りに“見られている”田舎の環境とそこでの発病
──ナルコレプシーを発病されたのはいつ頃ですか?
増川 高校一年のときだと思います。その頃、昼間の猛烈な眠気と変な夢を見るというのがはじまりました。始まりは・・・「意識のレベルが下がる」という感じ、常に寝不足のような意識状態。朝起きてどんなに時間が経っても、エンジンがかからない感じ・・・とても怖かったです。どんどん意識のレベルが下がっていって、ついには授業ではまったく起きていられなくなりました。授業が始まると、5分もしないうちに寝ていたと思います。「今日は、今日こそは起きていたい」と思っても、無理でした。そして、ただ眠るだけじゃないんです。ああ、今先生はこう言っているんだな・・・そうか、、と思っていると、それは夢なんです。私はいつの間にか夢を見ているんです。そしてはっとして、また授業に集中、と思って話を聴いているのですが、それもまた夢で。そして、気がつくと本格的に眠っているんです。それは、体育などを除くと、どんな授業でも。あ、もしかしたら、体育の時も変だったと思います。力の入れ方がわからなくなっていましたから・・・そういえば、水泳の前とかは、着替えたらちょっと横になって寝ていたと思います。そうしないと危ないと思ったので。
また、私は文学好きで、中原中也や高村光太郎の詩が好きでしたが、小説などの“長い”ものは読めない。読めなくなりました。まいりました。
「ああ、こう書いてあるんだ」と思っていても、それは夢。いつの間にか寝ちゃっていて、実際には「本を読んでいる夢」を見ているわけなんです。何も読んでいない。しかも、いつ眠ったか、自分でもわからない。現実と夢とは“一続き”なわけなんです。とても混乱しますし、とても困りました。自分もそうとわからないまま・・・いつの間にか眠っていて、いつの間にか夢を見ているわけです。
──ナルコレプシーであるという診断は、その頃つかなかったのですか?
増川 はい。私の人生にナルコレプシーという言葉が登場してくるのは大学で、上京してからですね。19歳でした。それまでは「絶対に何かがおかしい」と思いつつも、病院などに行くと「思春期はだれでも眠たいものだから・・・」のような説明しか受けられなくて、誰にもわかってもらえず・・・ほんと、何が起きているかがわからなかったです。ただ、頭が壊れていく・・・と思っていました。怖かったです。
──高校までは、どこでお過ごしになったんですか?
新潟県のかなり田舎の方です。そこは皆が互いを屋号で呼び合うようなところで、誰もが私のことを知っていますし、また、常に人に見られているという感覚もあった。それで、高校は街の進学校に行ったのですが、そうすると周りには自分のことを知っている人はほとんどいないし、自分を自分で人に説明しなくてはならなくなった。そこでバランスを崩したような気がしています。家での顔と学校での顔が違う子供に育ってしまっていて。そして、学校で人に話しかけられるのが嫌で、狸寝入りのようなことをしていたら・・・狸寝入りではなく、本当に起きられなくなってしまった。だから、私は、・・・それがナルコレプシーという病を呼び寄せたのだと思っていて。なので、今でも自分で自分の脳を壊してしまったと思っていて、、、どうしてもそこには、自責の念があります。家族に本当に、本当に大事に育ててもらったのに、親とか、ご先祖様に悪いことをした・・・という想いです。みんなで大事にしてくれたものを、私が、私自身が壊してしまった・・・。
「命だけが残ってしまった」
──そんな中でも、東京の大学を受験し、合格されたわけですね。
増川 私としては「常に回りから見られているような環境」から脱すれば自然と眠気も収まるだろうと思っていました。なんとかしないといけない、って思っていましたから。また、文学で身を立てたいという野心もあった。それで一浪してなんとか東京の大学に入ったのですが、いっこうに症状は治まらない。加えて駅のホームなどを歩いているとホームがぐにゃぐにゃ曲がるような感覚に襲われるようにもなりました。困りきって、学生相談室に行って週に一度・・・かな、臨床心理士さん(詳細は不明)に話を聞いてもらっていたのですが、そこで精神疾患の疑いがあるから精神科クリニックを受診するように勧められたのです。そのクリニックではじめてナルコレプシーの疑いありという診断が出され、大学病院で精密検査を受けました。ただ、そこではナルコレプシーという診断は下されず、「突発性傾眠症」ということでリタリンという向精神薬を頓服として服用するようになりました。ただ、リタリンは効いているときは眠気が覚めていいのですけど、切れたときに不安感が強く出て、それが辛くてあまり使いませんでしたし、完全に服用を止めていた時期もあります。
話は変わりますが、私、21歳のときに結婚して大学を中退しているのですね。それで、仕事をしなければならなくなったのですが、私としては文学で身を立てるためにすべてを捨てて東京に出てきたという思いもあり、どうしても仕事をするという気にはなれないところがありました。気持ちとしては、「売れない詩人」と自分を見ていたので、世間でいう仕事は、あくまでも食べるための手段。本職は詩作と思っていました。全然食べられないのに・・・ですね(苦笑)。それで仕事を転々とする日々が続く中、一緒に活動していた詩のグループの人から「自分の得意な分野で仕事をした方がいい」と言われ、日本語教師養成学校に通い始めたのです。学費の大半は奥さんが出してくれました。しかし、ひどい眠気で授業中も起きていられなくない状態で、とても勉強に身が入らない。ただ、学費を彼女に出してもらっている以上、後には引けないし、そこでもう一回検査を受けようということになって、千葉県にある国立の精神・神経科の研究で有名な病院で精密検査を受けたのです。そこではじめて重度のナルコレプシーという診断が下されたのですね。これでは社会生活はとても営めないだろう、と。27歳のときでした。
──そうした宣告をうけたとき、どのように受け止められましたか?
増川 まず、自分の置かれている状況にようやく合理的な説明がついたということで、ほっとしましたね。ただ、現代の医学では原因がわからないし根本的な治療法もないといわれたことには絶望しました。しかし、その一方で、社会生活は営めないだろうといわれて、肩の荷が下りた感じがしたのです。
対処療法としては、やはりリタリンの服用しかないということで、その服用を再開し、日本語学校での勉強を始めました。このときはリタリンが以前よりも安定的に効き、無事一年で日本語学校を卒業しました。試験にも一回で合格しました。嬉しかったですね。でも、日本語教師の資格を取っても、私は大学を中退していますから、学歴の壁に阻まれて仕事がないんです。困っていたところを助けてくれたのが、日本語ボランティアの活動を通して知り合ったある広告関係の会社の社長でした。「言葉が好きなら広告の仕事をやるのもいいかもよ。ちょうど、事務所を拡大させようとしているところでね。うちで働いてみない?」と自分の会社に私を誘ってくださったのです。そして、そのタイミングで奥さんがワーキングホリデーを活用して海外に出ることになり、私は私で、こちらで一人ががんばろうと思いました。
ただ、私の方の仕事はだんだんと、しだいにうまく行かなくなっていきました。リタリンが効いている間は普通に働けるのですが、切れるとパフォーマンスが極端に落ちてしまうのですね。それで、こんなに仕事にムラがあっては困るということで、約一年で退職ということになりました。薬を上手く使えば社会生活を営める──そんな風に考えていたところに、自分はやはり社会では通用しないという現実を突きつけられて、本当にショックでしたね。海外にいる奥さんには「これから新しい人生がはじまる。仕事もちゃんとするから」と言っていたのです。それが全部、壊れてしまった。
それでも、そのときは一人でしたので、なんとか自分で生計を立てなければならない。市役所に相談に行って障害年金というものがあることを知り、まずはこれを受給しようということになりました。ただ、詳細は省きますがナルコレプシーという疾患名で障害年金を受給するには大変な苦労が伴いました。それであちこち奔走し、苦労を重ねる中で、私はリタリンをはじめとする薬物を乱用するようになっていました。最後には完全な薬物中毒。結果的に年金は一級を受給することができ、月額約8万円の支給額を得ることになったのですが、そんな額ではとても生活できない。奥さんに帰ってきてもらい、彼女が働くことになったのですが、彼女が帰宅すると私が薬切れで暴れている──そんな状態が一年ぐらい続きました。
奥さんと世帯分離して生活保護を受給することを考え、何度も行政に訴えましたが、それは叶いませんでした。「離婚してから来てください」「いいえ、私は離婚はしたくないのです。世帯分離でお願いします」 そして、本当にもう駄目だと思ってまた市役所に相談に行くと、「離婚することにしましたか?」そんなことを言われていました。そして、担当の人とその上司と、家にも来ていろいろ言われたことがありました。この辺のことを思い出すと今でも具合が悪くなるのですが、最終的に奥さんと離婚し、私は一人で生活保護を受給することになりました。一人になったときに、「命だけが残ってしまった」と強く思ったことを覚えています。
ほんと、すべてを剥ぎ取られ、私はなんにもなくなっていました。夢を持って出てきた都会で、家族も・・・10年一緒に暮らしてきた妻もいなくなり、病気は前からあったのでちゃんと生命保険をかけていたのですがそれも生活保護に伴い解約、、、お金も使い切ってから・・・残金が20万円を切ったら来てください、ということだったので口座にお金もなく、、そして、一番きつかったのは・・・離婚してから来てください、と、そして、親に連絡が行き、「息子の面倒を見る財力が家にはないから、生活保護の申請をお願いします」と親に言わせたことでした。そして、親からの仕送りも、それが野菜やお米であってもダメということで、、、私は、それまでのつながりを・・・なくしました。なので、こんな命、要らないと思いました。生きていても、病の症状はあるんです。そして、病の症状しかないんです。ほんと、大事に想ってきたもの、そこにずっとあるって思っていたものがみんな、剥ぎ取られてしまった。そして、ぽつんと、地元ではない町で、一人になりました。薬物中毒の体で。私に残ったのは、障害1級と診断された証書と生活保護の資格だけでした。30歳を過ぎていました。
病の体験があるからこそできることがある
──その頃、病状はどうだったのですか?
増川 ひどかったです。薬物中毒で体が動かなくなって、寝返りひとつ打つことが出来ない。買い物などはどうしていたかというと、リタリンを大量に服用してなんとか体を動かせるようにして、タクシーに乗って、大量の食物を買ってくる。ほんと大量の冷凍食品と飲み物と、パン──そんな感じでした。
また、その頃は自傷などもひどく、衝動的に飛び降りたいとなることも多くて、「でも死にたくない」って、飛び降り自殺をしないように自分の体を針金でぐるぐる巻きにしたりしていました。
──そこから、どうやってリカバリーしていったのですか?
増川 すごくいろいろ調べました。市や県やそして、厚労省に相談しました。インターネットで調べて、助けてくれそうなところに繋がりました。そして、地元のソーシャルワーカーさんにつながって・・・。やがて、そのソーシャルワーカーさんを通じてホームヘルパーさんが自宅に来てくれるようになり、家事などをやってもらえるようになって少しほっとした感じです。何より良かったのは、食料の確保が安定的にできるようになったこと。それは大きいことでした。都会で暮らしていますが、その頃は、私は飢えと渇きがひどかったんです。食べ物、飲み物が手に入らない・・・これは本当に苦しかったです。そして、家に来ていたホームヘルパーさんが、私が在住していた千葉県市川市に新しい福祉事業所ができたから行ってみないかと教えてくれたのです。で、早速行ってみると、そこがガラス張りの建物で非常にきれいだった。それまでも福祉施設に行ったことはあるのですが、どれも古い建物で、うらぶれた感じがしてどうしても通う気にはなれなかった。でも、その市川の施設なら通ってみてもいいかなと思ったのです。
──それは、どういう施設だったのですか?
増川 アメリカのクラブハウスモデルを取り入れた施設でした。クラブハウスモデルとは1940年代のアメリカで始まった精神障害者の自助活動による相互支援を基盤とした活動で、その特徴は運営維持のための仕事をメンバーと呼ばれる利用者とスタッフがともに行うことにあります。私にとってラッキーだったのは、マディソンモデルといわれる新しい精神保健サービスシステムを、その発祥の地であるウィスコンシン州と千葉県が姉妹都市であることから、同県に持ってこようとしていたところであったこと。そのモデル事業を、国立の研究所があった市川・・・私が住んでいる町ですが・・・その市川市で、先ずは展開しようというところだったことです。ほんと、いいタイミングでした。で、「マディソンモデル活用事業」の一つのメニューとして、「クラブハウス」があって、そのクラブハウスを家に来ていたヘルパーさんが紹介してくれたのです。そして、そのクラブハウスにはじめて行ったとき、「ここは何をするところなのですか?」と訊いたら「何をやるかはメンバーであるあなたたちが決めてください」、と。何でも自由にやっていいというわけです。「箱は用意しました。中身は、メンバーであるあなたたちが決めることが出来るんです」と。それを聞いて、たとえば以前、携わっていた広告の仕事なども生かせるかもしれない、社会の中にまた役割を持てるかもしれないと思い、非常に嬉しかったですね。
──それが一つの転機になったわけですね?
増川 はい。そして、私の転機はもう一つ。これがとても大きいのですが、そのクラブハウスではじめて同じ病の友人ができたこと。病気のことなど何も説明せずとも「ああ、それわかる。俺もそういうことあったからさ」とわかってくれる友人の存在は、私にとってかけがえのないものになりました。で、その友人たちとクラブハウスを使ってなにかイベントをやろうということになった。ちょうどクリスマス時期だったのでクリスマスイベントを企画し、準備期間わずか二週間たらずだったのですが、地域の方の参加も呼びかけて開催することができたのです。その成功を基にいくつかイベントを立ち上げていきました。それらは当初、クラブハウスメンバー有志のイベントだったものが、クラブハウスそのもののイベントになっていきました。同時に、私自身はマディソンモデル活用事業の委員に入れてもらったりして、「病気があってもできることはたくさんある」「病気の経験があるからこそできることがある」──今はまた違った考え方をしていますが──と思うようになってきた。そんなタイミングで「ピアサポート」という言葉を知りました。仲間同士の支え合い。そして、私はクラブハウスでの活動とともに、仲間と、プロジェクトRという団体に関わるようになっていきます。ジャーナリスト、看護師、そして私たち当事者たちの仲間で、「経験を力に変える!!」というコンセプトでワークショップを行うようになりました。メンタルヘルスワークショップ集団。それが、プロジェクトRです。オリジナルのコンテンツも作っていました。アメリカの当事者の方を招いてのワークショップも行いました。日本ファシリテーション協会の方を講師に、本格的なワークショップも行いました。そんな折りにアメリカから精神障害当事者でWRAPのファシリテーターであるジーニー・ホワイト・クラフトという人が来日し、お話を聞く機会を持ったのですが、実際にピアサポーターとして生計を立てている人に出会った経験は、私にとって決定的なものでした。
──ご自身もピアサポーターとして生計を立てたいと思うようになったわけですね。
増川 はい。そして私はジーニーさんとの出会いで、WRAPにも取り組むようになっていきます。
──WRAPというのはどういうものですか?
増川 アメリカの精神障害当事者であるメアリー・エレン・コープランド氏を中心に、同国の精神障害を持つ人たちによって作られたリカバリーに役立つ仕組みです。ここでいうリカバリーは①希望②責任を持つこと③学ぶこと④自分の権利を守ること⑤サポートという5つの重要な考え方によって成り立っており、WRAPを学ぶ者はそれらに沿って自分の経験をいわば棚卸ししていくわけです。その中で、自分なりのリカバリーの方法論を導くこと──最近では「WRAPは自分の取扱説明書」なんて言い方よくされていますが、簡単に言うと、それがWRAPの概要になります。
そして、これもラッキーなことに、翌2007年に福岡県久留米市でWRAPファシリテーター養成研修」があると聞き、なんとか研修費を工面して参加。トレーニングを受けて「WRAPファシリテーターの資格を取りました。ただ、資格を取ったといってもそれですぐに収入に結びつく仕事を依頼されるわけではない。月に一回、仕事があるかないか、年に一回、学会に呼ばれて講演をする機会があるか、ないか・・・。
「これで食べていきたい」を見つけたものの、なかなか道は開けない・・・。焦りました。私は、もう34歳とか、そのあたり。同年代の人たちは結婚して子供を持ち、会社でのポストも上がって順調にキャリアを築いているのに、自分はいつまでたっても生活保護受給者。健常者が眩しく見えて──苦しかったです。首吊りをしていたところを発見されたりもありました。やはり、おいてけぼり感は、きつかったですね。どんなに頑張っても報われないという感じ・・・ そして、みじめな感じ、、、 そうすると、やっぱり病気にならなかったら・・・と思うし、こんな体やだというのが強くなっていきました。
──今の増川さんの姿からは想像できませんね。
増川 ですかね。そのとき支えとなってくれたのがプロジェクトRの仲間たちをはじめとする友人たちです。また、私自身、自分のWRAPをきちんと作って、具合が悪くなったときはそれを見直したりして──WRAPというのはいわば自分の取り扱い説明書。私の病気は現代医学では治せないといわれています。けれども、、、しかし、メアリー・エレンさんの調査によると、リカバリーというのは確かに存在していて、・・・そのことを知ってからは、私は変わったと思います。では、自分はどうなのか?──それをひたすら問いかけてきたのが私のこの10年だったと思います。いま考えると、この10年、私は「学生」だったと思うのです。自分のWRAPをつくり、自分自身のリカバリーを見つめていくと同時に、このツールとピアサポートについて試行錯誤しながら、実践しながら、ひたすら学んだ。そうしているうちに、2010年ぐらいからでしょうか、少しずつWRAPクラスの依頼が入ってくるようになってきて、そのうちの一つが東京ソテリアの地域活動支援センター「はるえ野」でのプログラムでした。で、その後にソテリアから「ソテリアとしてもピアサポートに力を入れていくことにしたので常勤職員として来ないか」とお誘いを受け、今にいたるわけです。
恢復(リカバリー)の経験を持てたからこそできることがある
──ピアサポーターの重要性が強調されつつも、なかなか実際の雇用には結びつかない現状を考えると、東京ソテリアには先見の明があるといえそうですね。
増川 ありがとうございます。それは嬉しい評価ですね。
ピアサポーター・・・何が優れているかというと、察知能力ですね。似たような経験をしているからこそ見えるものというのがあると私は思います。たとえば、私がいま勤務している系列のグループホームにも何人かのピアサポーターがいるのですが、みんないろんな人の出すサインを本当に敏感に察知する。それも、外側から観てではなく、「当事者」としての視点で観ることが出来るというのは、やはり違うと思うのです。そうした能力を・・・きちんと評価し、そこにお金をつけた上で活用していく・・・ソテリアのその姿勢はほんといいと思っています。口だけではない感じ。本当に、ピアサポートを評価していると思うのです。
また、働く側の立場から言わせていただくと、非常に働きやすい。たとえば今も私は、眠気がひどいのですが、頭をクリアにしなければならないときには、仮眠を取らせてもらえます。これが一般的な会社だと、仮眠など非生産的であるとしてリタリンを飲んで働くことの方を奨励されるでしょう。社会規範というか、一般通念が支配的。もちろんそれは合理的で意味ある事とは思うのですが・・・その結果、病がより深刻化してしまう。ということってあると思います。でも、今の職場は個別の、それぞれの「人」を観てくれて、それを基盤に仕事をしていくという姿勢なんです。まず「人」がある感じです。
──増川さんの今の病状はいかがなのでしょう?
増川 具合が良い・悪いで言えば、決して良くはありません。たとえばいま困っているのは、きちんと歩けなくなってしまったこと。歩き始めの一歩を左右どちらの足で踏み出したかがわからなくなると混乱してしまう。そうすると元の場所に戻ってまた歩み始めなければならなくなります。非常に不便です。それでも、仕事があるから何度でも歩き直すのです。以前、よく言われていたのが「病気がよくなってから仕事を探しなさい」ということ。いま考えると、これは逆です。仕事があるから、しっかりしようとする。仕事があるから、症状となんとか共存しようとする。もし、いま私に仕事がなくなったとしたら、また元のひどい生活に戻ってしまうような気がします。やはり大切なのは、「仕事と友達」ですね。私はいま、ほとんど自傷行為をしませんが、それは大切な友達に嫌な想いをさせたくないからです。大切な友だちを怖がらせたりしないためです。友達が一人もいなかったら、自傷行為が止むことはなかったと思います。ひとりぼっちでは、「自分の体は自分の体、、、以上」、だった。今は、違う感覚があります。私が大事に想う人のために、私は自分の体を大切にしようと想っています。その人を悲しませたくない、それが本当に大きいんです。
──最後に読者へのメッセージをお願いします。
増川 私の考え方はいくつかの変遷を経てきています。最初は病気があるからダメなんだ、病気さえなければ人生もっと上手くいくのにと考えていました。次に、病気の体験があるからこそ出来ることがあるに変わりました。いずれにせよ、病気を根拠といいますか、拠り所にした考え方でした。しかし今は、「恢復(リカバリー)の経験があるからこそできることがある」に変わりました。
「根拠は、「病気の体験」ではなく、「リカバリーの体験」」
「根拠は、「病」ではなく、「リカバリー力」」
この変化は、私の人生においても、仕事においても、大きな変化です。
私がいま伝えたいのは、病気があっても人生リカバリーできるということ。
なぜならば、人には「自分を」リカバリーする力があるのだから。
人生、苦しいことなどどんな人にもありますが、それがあっても、人には自分をリカバリーさせる力があるから、それを発動させて自分をチューニングしなおして前に進むことができる、そのことを最後に強調しておきたいと思います。
「誰でも、誰にも、リカバリー出来る力が備わっている」
それが、私が自分の人生を通して知ったことです。みなさんのその力、どうぞ存分に使ってください。そうしたら、人生は開けていきますし、みなさんのその行動で、リカバリーで、世界はどんどん良くなっていくって、私は思うんです。
──どうもありがとうございました。
増川 ありがとうございました。
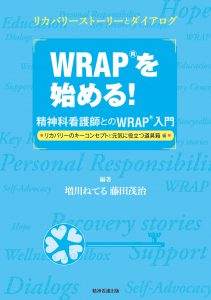
WRAPを始める!
―精神科看護師とのWRAP入門
【リカバリーのキーコンセプトと元気に役立つ道具箱編】
著者:増川ねてる、 藤田茂治
