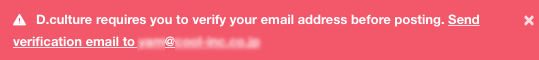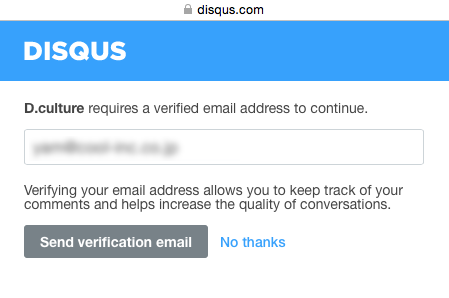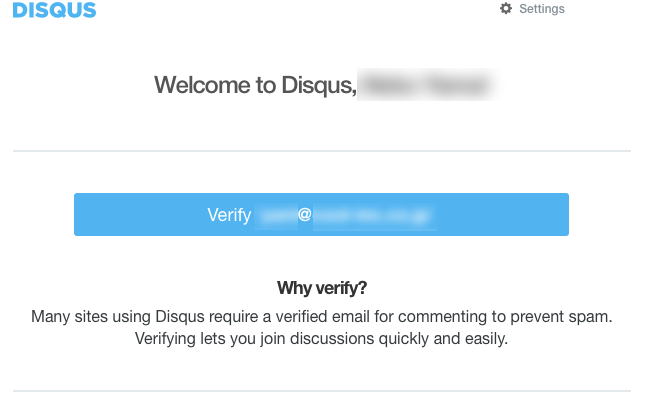水戸川真由美さん
[公益財団法人日本ダウン症協会 理事]

障害のある子が「おしゃれをしてもいいじゃない!」
「最近の若い(ダウン症のある子供の)お父さんやお母さんは本当にエネルギッシュでパワフル。障害のある子供を持つことからくる悲壮感や暗さは感じられなくなりましたね」
開口一番、水戸川さんはそう語りはじめた。ダウン症(正式には「ダウン症候群」)の臨床像がWHOによって医学的に確定されたのは約50年前。以降、ダウン症で生まれてきた人たちとその家族は、やはり長い間、周囲の無理解や偏見などを感じ、いわれなき活きづらさを抱えて人生を送らざるを得ない状況に置かれてきた。その状況がここ十数年で大きく変わってきているという。
一つには、一般に向けてのダウン症に関する啓発が進み、ダウン症のある人たちの“生き方”や“育て方”への理解が広まってきたことがある。ここ日本においては、そうした状況変化へのJDSの寄与は少なくない。ダウン症に関する知識の普及啓発、情報の提供、調査研究、また当事者とその家族に対する相談事業などを通じて、JDSは当事者とその家族のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上に努めてきた。具体的な活動について、水戸川さんはこう語る。
「さまざまなセミナーやイベントを通しての普及啓発活動や、国への制度面の整備の訴えかけなど、JDSの取り組みは多方面にわたりますが、一つの柱としてあるのが相談事業ですね。はじめてダウン症の子供を授かった親御さんというのは、いろいろなことがわからないわけです。わからないからこそ、不安になる。この子は歩けるんでしょうか? 喋れるようになるんでしょうか? 将来どうなるんでしょう?──そうした不安から生じる疑問に、相談員が一つひとつ丁寧にお応えする。また、地域の情報提供なども重要ですね。たとえば、相談者の方と地域の親の会を繋いでいくこと。とにかく、当事者や親御さんが孤立し、悩みを一人で抱え込まないようにしてさしあげることが大切だと思います」
そうした地道な取り組みの一方、JDSはダウン症に対する従来のイメージを大きく変えるようなイベントなどにも関与している。たとえば「LOVE JUNX(ラブジャンクス)」というダウン症のある人たちのための世界で初めての本格的なエンターテインメントスクールとのコラボレーションにより、12年前に横浜で開催されたHIPHOPダンスの全国大会もその一つ。一般にダウン症のある人たちというのは低緊張であり、頸椎などに影響を受けやすいケースが多いため、激しい運動は出来ないとされてきた。そんな彼ら・彼女らが、激しいビートに乗ってHIPHOPを生き生きと踊る。その姿は数々のテレビ番組をはじめ、さまざまなメディアに継続的に取り上げられ、ダウン症──ひいては障害者全般に対する世間の見方を一変させるターニングポイントになったと、水戸川さんは言う。
「障害のある人というと、なんとなく暗いイメージがつきまとうわけですよ。こう、“おしゃれしちゃいけない”みたいな。そんな彼ら・彼女らが最新のファッションに身を包み、最先端のHIPHOPを楽しく踊る。そうすると、世間の障害者観が変わるわけです。障害のある人のご家族に限らず、あのステージを見ると元気が出るという声が多い。障害のある人でも明るく、開放的に、その人らしく楽しく生き生きと暮らせるんだということを発信できたことの意義は非常に大きかったと思います」
「障害のある人がおしゃれをしてもいいじゃない!」と水戸川さんは続ける。障害を抱えた人生をネガティブにではなくポジティブに生きる──彼女の言葉の底流には、そんなメッセージが流れている。
自立の“あり方”は多様であって良い
さて、そんな水戸川さんご自身も障害のある子供を授かった母親の一人だ。現在32歳の長女は脳性まひで知的にも遅れがあり、完全看護。次女はハンディキャップを持たない子供。そして、17歳の長男はダウン症のある子供である。二人の障害のある子供を抱え、育てる──一般には「さぞかし大変だろう」と同情を寄せられがちなところだ。だが、「それは考え方次第」と水戸川さんは言う。
「脳性まひの子、ハンディキャップのない子、ダウン症のある子と三人の子供がいますが、実際に育ててみると、子育ての大変さも、そこから得られる喜びも、それぞれの子供によって違います。言ってみれば、どの子の子育てにも同じように大変さと喜びが備わっている。ですから、三人の子供を比較することはまったく無意味。たとえば長男に関していうと、まずウチの息子というのがあって、たまたま彼にダウン症があったという位置づけです。彼のいろいろな行動に関しても、“ダウン症だからそうね”というのではなく、彼の性格によるものだと考えています。性格をダウン症のせいにすることはできません」
ただ、その子の持つ特性によって、育て方にはやはり違いが出てくる。「これはその子に障害があるかないかに関わらず言えることですが」と前置きしつつ、わが子を育てる上では「斜めの関係がとても大切」と水戸川さんは言う。「斜めの関係」とは、いわゆる親子関係以外の関係性──ヘルパーなどを含む周囲の子育て協力者との関係性のことである。障害のある子を授かった親にありがちなのは、「この子は自分が守らなければ、私でなければ」と思いがちになり、子供の面倒に関して第三者に協力を求められなくなる傾向。それは、その子供自身にとっても親にとっても向上を妨げる要因になる水戸川さんは説く。たとえば、親が言って聞かせるよりも「斜めにいる人(たとえば、お友達のお母さん)」の言葉の方が、その子供にとって説得力を持つこともある。また、子供というのは親以外の「仲間」と一緒にいてこそ成長するのだとも彼女は言う。
「ウチの場合、たまたま私が仕事を持っていたということもあって、脳性まひの長女などに関しても、小さい頃から周囲の人に子育てを協力してもらっていましたし、ショートステイなどにも行かせていました。ですから、私の手からだけでなくいろいろな人の手からモノを食べるし、外に泊まることにも馴れていたのですね。長女はいま、施設に入所していますが、施設の環境を抵抗なく受け入れ、生活していけるのは、やはり小さい頃から斜めにいる人に面倒を見てもらう経験を重ねてきたからだと思うのです。いろいろな人の協力を得ながら生きていける状況──私は、それが長女にとっての“自立”だと考えています」
「そして、なにより、私自身が複数の斜めの関係の方からの支えによって心のサポートを受けてきました。だからこそ、今の私があります。本当に感謝に堪えませんね」と水戸川さんは続ける。障害のある子供を授かった親にとって、いちばんの気がかりといえば、やはり子供の自立の問題だろう。だが、「いろいろな自立の形があっていい」と水戸川さんは言う。自分一人の力で生きていけることだけが自立なのではない。たとえば親以外の第三者にきちんと生活を支援してもらえる、そんな状況を形づくることもまた、自立の一つの形ではないか。この提言は、水戸川さんご自身が障害のある子の親であるだけに、強い説得力を持つと筆者は思う。
最後に、障害当事者とその家族に向けてメッセージがあればと訊ねてみた。
「障害のある人をはじめとするマイノリティを支援する組織・Get to touchを主催されている女優の東ちづるさんは、いろいろな“ちがい”をもった人が自然に、自由にまじりあう「まぜこぜ」の社会を提唱していらっしゃいますが、同じような意味で、私は“心のボーダーをなくそう”をキャッチコピーにしています。ひとくちに障害といってもその形はさまざまで、ひとくくりにはできません。でも、そうした障害の種別を問わず、お互いが相手を尊重する。人間一人ひとりの個性というのは、決して比較の対象ではないのです。それは、障害者と健常者の間であっても同じです。心のボーダーを失くし、いろんな“ちがい”をもった人がごちゃまぜになれる社会。つまり、みんないっしょな社会。私もそれが理想の社会だと考えています」